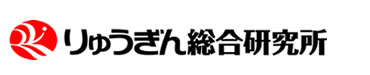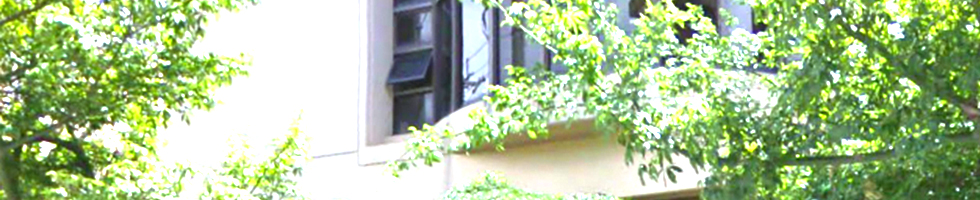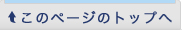調査レポート
沖縄県内における自治体・災害実動機関の連携強化を目的とした SIP防災実施について〜沖縄県のスマート防災ネットワーク構築に向けて〜
<要旨>
•本レポートは、2025年3月に当社が発信した「沖縄県のスマート防災ネットワークの構築に向けた提言」に基づき、主催者である防災科研と共に「SIP防災OKINAWA2025」の実施を公表するものである。本イベントは、SIP第3期「スマート防災ネットワークの構築」サブ課題C「災害実動機関における組織横断の情報共有・活用」において、開発中のシステム群の有効性を、沖縄県を実証の場として実践的に検証し、県内の自治体・災害実動機関の連携強化を図ることを目的にしている。
•迅速に災害対応を行うには、関係者間の災害情報の共有が必要不可欠である。昨年11月に沖縄県北部地域で発生した豪雨災害では県の防災情報システムは有効に機能しなかった。これは、利用者が限定されていることに加え、被災地の自治体職員が入力する災害情報をもとに災害対策本部が機能するという体制そのものに課題があると考えられる。自治体職員は、住民の問い合わせや避難所対応等に追われ、情報入力は後手になるのが実状である。この状況を維持することは、災害状況の全体把握が困難になり、支援の遅れや被害拡大を招くことにつながる。
•「スマート防災ネットワークの構築」サブ課題Cの研究では、災害情報の共有を消防・警察・自衛隊などの災害実動機関に協力を仰ぎ、自治体職員が情報入力せずとも被災地全体の状況が把握できる取り組みを行なっている。また、各機関隊員の災害情報の入力負担軽減等を図るため、音声認識や画像認識、生成AIやドローン等を活用したシステム群の開発も進めている。
•沖縄県は、東西約1,000km、南北約400kmに及ぶ海域に市町村が点在する広大な海洋島嶼圏である。本島・離島間の連携や情報共有は常に課題である。また、懸念されている南海トラフ巨大地震等の発生時には、本土からの受援が困難になる状況が容易に想像できる。そのために、平時から沖縄県内の各機関が迅速に連携できる体制やデジタル基盤の構築が急務である。
•2025年12月に沖縄県で実施する「SIP防災OKINAWA2025」は、災害専門機関である防災科研が中立的な立場で県内の自治体・災害実動機関と連携し、大規模災害発災時の合同調整を検証する「全国初」の合同訓練を予定している。