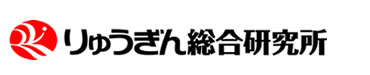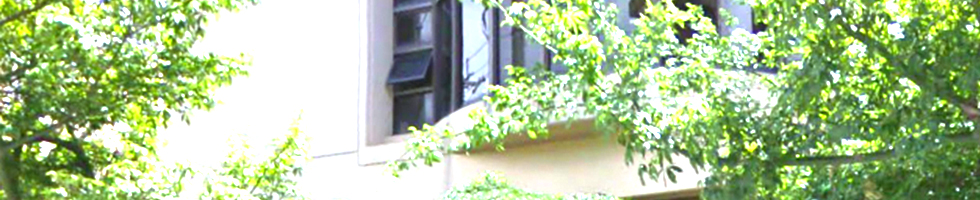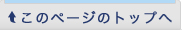調査レポート
沖縄県における一戸建て住宅着工の動向と県内住宅市場の今後の展望 ~木造住宅がRC造住宅を逆転、住宅市場は大きな転換期~
≪要旨≫
・沖縄県の一戸建て住宅は従来鉄筋コンクリート造(RC造)住宅が主流であり、総務省「住宅・土地統計調査」によると県内における人が居住する一戸建て住宅については、2023年10月時点で鉄筋・鉄骨コンクリート造が85.4%を占める。一方、全国的には木造住宅が主流であり、この特徴は本県独自のものである。
・足元では木造住宅の着工戸数が年々増加しており、2023年度に新設された一戸建て住宅の着工戸数は、木造が1,722戸、RC造が1,368戸と木造がRC造を上回る状況がみられた。特に木造分譲住宅がシェアを伸ばしており、背景には人件費や地価の高騰等による住宅取得費の増加のなかで県外大手ハウスメーカーの参入があり、安価な木造分譲住宅に需要が流れているとみられる。
・こうした状況のなか、RC造住宅の更なる発展に向け、まず、近年自然災害が多発していることに着目し、耐震性・耐火性に優れたRC住宅の県外展開の可能性を調査した。しかしながら、住宅関連企業へのヒアリングからは、顧客ニーズの観点から価格が比較的高いRC造住宅は選ばれにくく、気候の違い等によるハードルもあり、得策ではないことがわかった。
・続いて、RC造住宅を扱う企業へヒアリングを実施し、RC造住宅の県内シェアを維持・拡大させるための戦略について調査した。価格を抑える工法や省エネ対応、顧客への対応等、各社の差別化戦略について整理したほか、調査からは住宅購入者に求められる目線や、住宅建築を取り巻く制度上の課題も見えた。
・住宅市場が変容するなか、購入者は価格のみならず、安心して長く住み続けられる住宅か情報を集め、長期的な目線での判断力が求められている。また、脱炭素と本県の気候特性を考慮した住宅の推進、RC造住宅の着工が減少することによる県経済への影響等、県全体で向き合うべき課題も多い。今後の住宅市場の動向を引き続き注視していく必要がある。