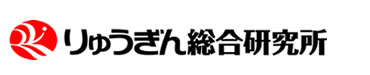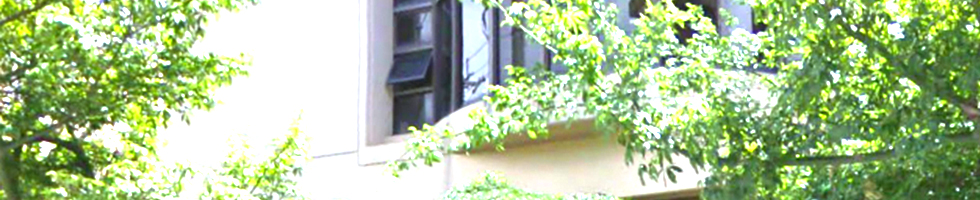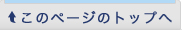調査レポート
沖縄県のスマート防災ネットワークの構築に向けた提言 〜北部豪雨災害等の対応から学ぶべきこと〜
<要旨>
•2024年11月9日未明、沖縄本島北部から鹿児島県与論町にかけて断続的に線状降水帯が発生した。東村では観測史上最大となる降水量を記録するなど、豪雨の影響は県内各地で多くの被害を発生させた。特に本島北部地域では土砂崩れや道路寸断、河川氾濫などが起き、住民の一部は避難を余儀なくされた。幸い人的被害はなかったが、ここでの災害対応は被害の拡大を招きかねない、多くの課題を浮き彫りにした。
•特に課題となったのは、沖縄県の初動対応の遅れである。行政界をまたいだ災害発生を確認していたが、県に「災害対策本部」が設置されたのは災害発生から2日後の11月11日午前であった。設置の遅れは「災害救助法」の適用が困難になる事態を招いたが、一番の問題は、統一的な指揮系統がないため、関係機関の連携が取れず、対応が断片化する恐れがあることである。その結果として二次災害や被害拡大につながる危険性がある。
•また、災害対応時には、分散している様々な情報を一元的または一体的に集約し、多角的に状況を把握する必要がある。災害情報の共有や連携においては、関係者全員が「集約された情報」をそれぞれの災害活動に役立てられることが重要であり、刻一刻と変化する状況を正確に把握し、災害リスクを正しく認識する環境の整備が求められる。
•災害対応を迅速に行うためには、災害対策本部のデジタル化と災害対応現場のデジタル化の促進が必須である。双方のデジタル化を促進することで、災害現場の状況が迅速に連携されるだけでなく、連携された情報を対策本部が分析して、速やかに実動機関の情報支援に繋げることが重要である。
•防災科研では、日本の科学技術イノベーションを実現するために創設された国家プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の防災分野で、民間企業と共同で災害情報をつなぐ基盤を開発した。また、災害発生時には現地の災害対策本部に研究員を派遣し、開発した基盤を活用して災害情報を一体化する作業のサポートも行っている。その基盤は、防災科研などが実際の災害現場で活用し、フィードバックを受けて改良を繰り返していることで更なる進化を続けている。
•沖縄県においても、デジタル技術を活用し、スマート防災ネットワークの構築を進めることが求められている。その実現には、災害分野における豊富な知見と技術力を持つ多様な立場の人々が協力し、新たな価値を創造する共創領域での連携が不可欠である。