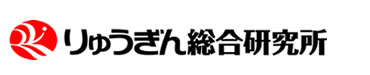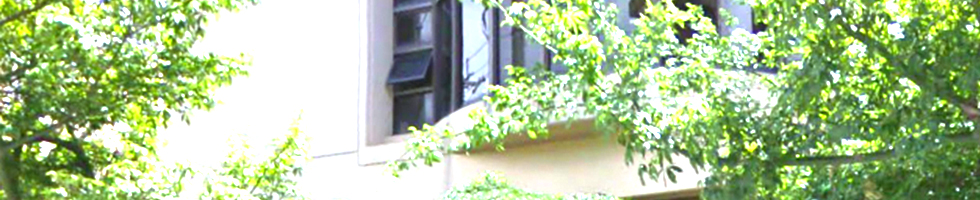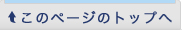調査レポート
沖縄県の労働市場の構造変化と今後の課題と展望 -2010年代以降の労働市場の7つの構造変化-
( 要 旨 )
・復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、1990年代まで低位で推移したが、2010年代に入ると県内景気の長期拡大により、求人数は増加基調が続いた。復帰後の有効求人倍率の推移をみると、12~19年は求人倍率が大きく上昇している。この背景には、県内景気の長期拡大に伴い求人数が増加するとともに、失業者が減少したことにより、求職者数が減少に転じていることがある。
・復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概ね7つの局面に分けることができる。直近の局面(2011年以降)は、県内景気の長期拡大により、失業率は改善傾向に転じ、18年にはほぼ全国並みになった。
・本県の労働市場の構造変化の一つは、2010年代以降の県内景気の拡大により、失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の状況となったことである。県内企業の欠員率は10年代に上昇を続けている。求人側である事業所の求人平均賃金は一貫して上昇傾向にある。
・労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割合が最も大きくなったことである。2023年の全産業に占める割合は15.6%と、産業大分類では最も大きな構成比となっている。当研究所の将来推計によると、今後、必要となる老人福祉・介護事業所の従業者数は、21年の2万8,606人から、50年には5万100人程度となる見通しである。
・労働市場の構造変化の三つ目は、需要不足失業が減少した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造的失業が高止まりしていることである。人手不足が深刻化する中で、労働需要が高まっているものの、求人側と求職側の希望や条件などのミスマッチにより、構造的な失業が解消していないことが窺われる。
・労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労働力人口の増加である。高齢者雇用安定法が施行された2006年4月以降は60~64歳の労働力人口が増加傾向に転じている。生産年齢人口が減少して人手不足が深刻化する中、高齢就業者の増加により、労働力人口は増加を続けている。
・労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働市場への参入の増加である。非労働力人口をみると、家事が減少傾向にあり、特に10年代後半以降は減少傾向が強まっている。更に本県では近年、女子の大学進学率が男子を上回り、女性の社会進出が増加していることも背景にある。
・労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就業者の増加である。県内の在留外国人も増加傾向にある。政府は単純労働の分野についても外国人労働者の受け入れを拡大するため、「特定技能」を創設した。分野別では、飲食料品製造が最も多く、次いで、介護、外食、農業、建設などとなっている。
・労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の変化である。足元の人口の減少数はまだ緩やかであるが、今後は少子高齢化の進展により、減少数が加速することが見込まれる。この人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最も大きな影響を及ぼす。また、今後は後期高齢者が増加することから、高齢者の参入も限界に近付くものと見込まれる。
・労働市場の課題としては、まず、少子高齢化、人口減少への対応である。当研究所の将来人口の推計によると2030年代後半以降は減少のスピードが加速する見通しとなっている。当面は人口減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕組みを考えざるを得ないが、より長期的な視点に立ったうえで経済社会を持続可能なものにするための様々な施策に取組み続ける必要がある。
・また、本県でも外国人労働者は増加しているが、県内で日本語などを勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流出している。基本的技能を身につけた外国人材が、その後も県内に留まるように、専門学校や外国人材の就労機会の拡充を進めていく必要がある。
・そして、今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に対しては、社会経済のデジタル化を進めていくことが不可欠であり、中高齢者のデジタル技術の活用に対するリテラシーの向上も不可欠である。また、労働移動の流動性を高めるとともに、親の介護や子育て支援なども含め、働き方の改革を一層進めていくことが重要である。