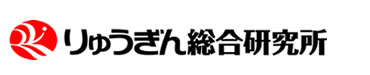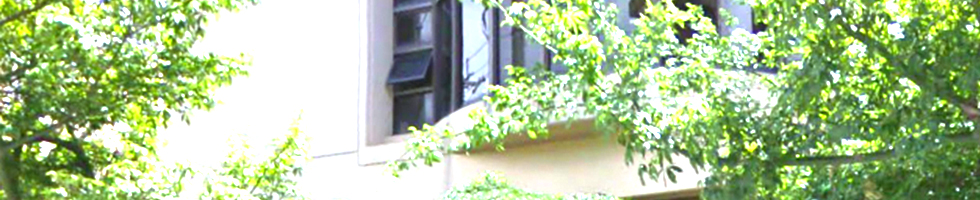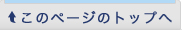調査レポート
コロナ後の沖縄県の景気動向~県経済は2023年度には、ほぼコロナ前の水準に戻る~
( 要 旨 )
・2019年末に新型コロナウイルスの感染が世界中に拡散してから、4年半余が経過した。本レポートでは、コロナ後の県内景気について、りゅうぎん景気動向指数(DI.、CI.)とりゅうぎん計量経済モデルを用いて、足元の景気動向と経済水準がコロナ前と比較してどの程度の水準となっているかをみた。
・景気の拡大、後退をみるDIを累積した累積DIで県内景気の動向をみると、東日本大震災が発生した後の2011年6月を底に持ち直し、回復に転じている。その後、インバウンドの増加や振興予算の増額、大型建設投資などにより長期の景気拡大が続いた。累積DIは19年9月にピークとなり、その後低下がみられる。そして、19年12月末には中国で新型コロナウイルスの感染が確認され、感染が世界中に拡大したことから、国内外の経済活動は大きな打撃を被った。本県の累積DIは大きく落ち込み、20年7月以降、横ばいで推移し、22年4月頃から上向いている。
・また、景気変動の大きさやテンポ(量感)を測定するCIは、東日本大震災が発生した後の5月を底に持ち直し、その後、長期に及ぶ上昇が続いたが、17年7月をピークに低下に転じ、景気の水準はまだ高いものの、減速し始めたことが確認できる。20年1月以降は新型コロナウイルスの感染拡大により、CIの値は急速に低下した。CIは20年5月を底に下げ止まり、21年7月頃から持ち直しに転じている。そして、CIでみた景気拡大のテンポは、22年11月にはコロナ前のピークとなった17年7月を上回っている。その後、CIは23年の10月から11月にかけて低下し、その後、翌24年の4月まで横ばいで推移したが、5月以降は再び持ち直しており、この期間は景気の踊り場であったとみられる。
・本レポートでは、DIを用いてヒストリカルDIを作成し、これにより県内景気の山と谷の時期(景気基準日付)についても特定した。この結果、本県の1977年以降の景気循環は6回あったとみられる。直近の景気の山と谷は、景気の山が18年12月であり、谷が20年12月であったと推定される。
・また、計量経済モデルを用いて、新型コロナウイルスの影響がなかった2018年度の経済水準を標準ケースとして、19~24年度までの入域観光客数と一人当たり観光消費額の減少や増加が県経済に及ぼした影響を試算した。試算結果によると、実質県内総生産は感染の影響が最も大きかった20年度から21年度にかけて両年度とも標準ケース比で▲7.9ポイントと大幅に減少し、その後は、マイナス幅が徐々に縮小し、23年度には▲0.2ポイントと、ほぼコロナ前の水準に戻っている。名目県内総生産や就業者数、完全失業率、消費者物価指数、税収などについても、20年度から21年度が標準ケースとの乖離幅が大きく、その後は改善傾向がみられる。22年度は、感染対策の効果なども浸透し、経済活動も回復の動きがみられた。そして、23年度には主要指標がほぼコロナ前の水準に戻っている。なお、今回の試算において、一人当たり観光消費額は政府の全国旅行支援などの施策もあり、比較的高額な宿泊施設の利用などから、むしろコロナ前より増加している。一人当たり観光消費額の増加は、入域観光客数の減少のマイナス効果をある程度相殺する政策効果があったといえる。